大変遅くなりましたが、本年もよろしくお願い致します。
アメリカでは毎年、1月にラスベガスで開催されるCES(CONSUMER ELECTRONICS SHOW)で主に電機産業界の幕が開く。今までは日本の大手家電メーカーが巨大且つ豪華な限りを尽くしたブースで他を圧倒していたのだが、ここ数年はその迫力も半減し、中国、台湾、韓国といった新興勢力に加え今年は自動車メーカーやIOTを中心とした各種デバイスメーカー中小規模の出展が増えたのが特徴だったようだ。 そして、その多様性と将来的な期待感もあってか、総来場者数も17万人に上ったという。
自分は会場に足を延ばしたわけではないので、具体的な雰囲気に触れることはできなかったのだが、色々なレポートなどを読むと、そこにはかなり近未来を予感させるようなものも多数出展されていたようだ。
いづれにしてもスマートPHONEの出現以降、電器産業を中心とした産業の流れは益々、加速度を増してきている状況を非常に強く感じる。 以前このブログでも触れたことがあるが、自分がアメリカに来た当初(今から約25年前)、こちらのTVで流れていたAT&TのCMは、近未来のライフスタイルというタイトルでシリーズで公開されていたと記憶しているのだが、買い物かごに満載された商品がレジの通路を通るだけで勝手に全てスキャンされて支払も全て自動で登録のクレジットカードに課金されるシステム、朝起きて洗面所(だったかな?)の鏡に顔をうつすと、鏡の中に組み込まれたタブレット型の端末がその日の健康状態を解析するシステム、車のエンジンをかけると設置されたスクリーンに全ての機関のコンディションやパーツの消耗具合を提示させるシステム等、当時としては想像可能な未来のテクノロジーを「私たちが実現します!」というかたちで結んでいた。 これらは今では既にほぼ実現(残念ながらAT&Tによるものではなかったけど…)できているような内容だ。このままいけば、数年もたたないうちに、このような環境は広く世の中に普及しているだろう。
今回のCESでは、IOTをテーマにした多くのデバイスが具象化され紹介されており、日本の電子関連の雑誌やメディアでも「IOT(ものインターネット)元年!IOTに注目!IOTが世界を変える!」といったような見出しが非常に目についた。これは確かに流れとして今後も技術的に具体化してくることは間違いないと思われるが、シリコンバレーでは既に昨年の半ばぐらいからIOTのスタートアップに投資するようなVCは激減しているのが現状だ。ここでは既に次のムーブメント探しに皆が躍起になっている。新しいものにトレンドが移行することで、テクノロジーの流れはどんどんスピードを上げているのだ。
さて日本はどうだろうか?年末の選挙では自民党が圧勝し、安部首相が再選となり、また継続してアベノミクスが続行される状況。 それによって国内需要が安定することは大いに結構。そして石破大臣を中心とした地方創生の具体案である「「まち・ひと・しごと創生構想」による地方の活性化も非常に意義のある試みだと思う。加えて2020年に開催予定のオリンピックに向けて、またリニアモーターカーの敷設など建設を中心とした国内の景気も堅調かもしれない。ただ、何となく内需の拡大による安心感というか安堵感がもたらすのは、ますます今の世界の流れから取り残されていくような感覚だ。
オリンピックまではあと5年。そこまで景気が良ければそれでよいのか?いやいや世界はその先に焦点を当てて走っているという事をやはり絶対に意識する必要がある。上記の景気対策でこの先5年は会社の運営も順調で推移しそうであれば、ぜひとも余力のあるところで10年後20年後を考えた計画を検討してほしい。自分たちの代だけでなく、子供や孫の生きる世界までを考えるという事が今は本当に重要。テクノロジーの発達はどんどん時間を短縮させている。10年なんてあっという間だ!
2015年は、世界の流れの速さに追従する意味でも皆さんには是非、グローバルな視野を持って世界の流れを体感し、少しでも10年後20年後を考える気持ちを持ってもらいたいと思います。

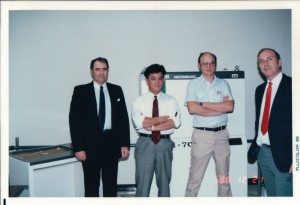
 米)BEANS International Corporation代表。 神奈川県出身。1988年に渡米。10年間の駐在員経験のあと1999年に独立しシリコンバレーにて起業。同地で一貫して次世代産業を支える製造業関連の仕事を継続し現在に至る。
米)BEANS International Corporation代表。 神奈川県出身。1988年に渡米。10年間の駐在員経験のあと1999年に独立しシリコンバレーにて起業。同地で一貫して次世代産業を支える製造業関連の仕事を継続し現在に至る。